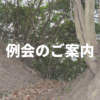丹波園部城と丹波亀山城を訪ねる(第743回例会)
●日時
令和7年9月7日 午前9時40分 雨天決行
●集合場所
JR園部駅西口
園部駅西口バス停9時49分発の京阪京都交通バスに乗車し、
園部高校前で下車(9時54分)後に受付。
弁当・飲物・敷物・帽子・ハイキング靴・タオル・雨具持参でお願いします。
マスクの着用は各自の判断でお願いいたします。
●行程
園部城大手櫓門 → 巽櫓 → 勘定所跡 → 巣鴨櫓跡・社後櫓跡 →
大手門跡 → 残存土塁 → 昼食休憩 バスの出発時刻まで自由
南丹市立文化博物館見学等 → 12時54分図書館前(国際交流会館)バス停
(南丹市コミュニティバス)乗車 → 園部駅西口着13時9分 →
園部駅13時16分発 → 亀岡駅13時31分着 → 丹波亀山城北側堀跡(南郷公園) →
天守台等見学 → 亀岡駅15時半頃解散
●参加費
賛助会員・正会員・家族会員 1100円
通信会員・当日参加者 1300円
(資料代・保険代・記念写真代・下見費用・丹波亀山城見学料300円)
●見どころ
【園部城】
但馬出石から園部に移封された小出吉親によって
元和5年(1619)から元和7年にかけて築城され、
以後、幕末まで小出氏10代の居城。
吉親は築城当初、櫓も建築しようとしたが、
幕府の許可が得られず陣屋の扱いとなった。
しかし、総構が南北約650m、東西約400mで二重の堀や鉄砲狭間を持つ
塀等もあり、規模としては城と呼べる規模。
幕末に至り園部が京に近く要衝の地である事等から、
最終的には明治新政府によって櫓などの建築が認められ、
明治2年(1869)に櫓門3ヶ所、櫓5ヶ所を持つ園部城となった。
明治4年(1871)の廃藩置県後は建物の多くは取り壊され、
府立園部高校の校門として利用されている櫓門とその番所、
巽櫓が残っているのみですが、無くなってしまった内堀跡、櫓跡や大手門跡、
現在も残存している腰巻石垣(下が石垣で上が土塁)等も確認したいと思います。
【丹波亀山城】
天正5年(1577)明智光秀が丹波攻略の拠点として築城したのが始まり。
本能寺の変後は豊臣系大名が、関ヶ原の戦い以後は徳川方大名が入り、
慶長15年(1610)岡部氏が城主の時、天下普請として藤堂高虎が縄張を手掛け、
近世城郭として完成。その際に藤堂高虎の今治城の天守が移築された。
その天守は五重五層、層塔型で当時としては例を見ないもの。
明治維新後は天守以下すべての建物が取り壊されただけでなく、
石垣もほぼ総て建築資材として持ち去られたが、
現在、城地を所有している宗教団体により石垣の修復と整備がなされており、
かつての亀山城の面影を見ることができる。
特に本丸跡東南面高石垣は下部が光秀築城期と推定できる
穴太積の特徴があると指摘されている。
また、城内には刻印を持つ石垣が50個以上確認されている。